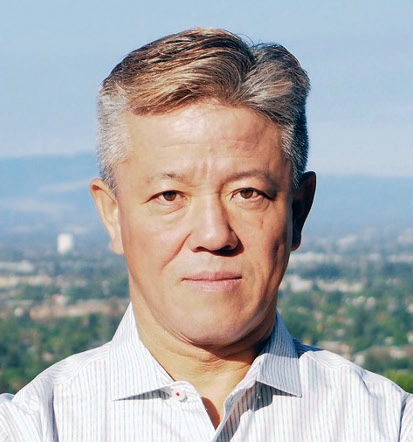World View〈アメリカ発〉シリーズ「最新シリコンバレー事情」第9回
アメリカの相互関税がもたらす功罪
2025年8-9月号
1月にトランプ政権が発足して以来、正直1日たりとも、アメリカから発せられるニュースに世界中が翻弄されない日は無いというくらい、トランプ政権が次々に発表する大統領令にカオスの状態が続いている。特に4月に発表された相互関税は一体何がゴールなのか? 勿論、公には「アメリカに製造業を戻し、生産性を高め、雇用を確保し、最終的にさらに豊かな国民性を確保する」というのが建前だろう。ただ、これにより、今まで細かな議論はありつつも一定の均衡を保っていた国際貿易の秩序が崩壊するきっかけとなっていることは否めない状況だ。

アメリカの相互関税政策は、原則としては特定の輸入品に対する関税を引き上げることで、国内の産業を保護することを目的としているが、ご存じの通りアメリカは輸入大国でもあり、輸入品に依存している産業や消費者にとっては、価格上昇という形で大きな影響が出ることは火を見るより明らかだ。
既にスーパーでは、野菜や果物の値上げが著しい。アメリカは農業大国で食品輸入率は約15%と低いが、アボカドやトマトなど人気の食品は、報復関税25%が課されているメキシコからの輸入品が多い。また、果物類や魚介類など、国内で生産が難しい食品の多くも輸入に依存している。衣料品の大部分も輸入品で、MADE IN USAのタグを見つけることすら困難だ。また赤ちゃん用品の90%が何と中国製。アメリカとの関税戦争の影響をまともに受けて、専門店では値札の付け替えが大変だとニュースが報じていた。
当然、輸入業者はそのコストを消費者に転嫁するようになり、輸入品価格の上昇が、結果として国内の物価全体の上昇を招くことは間違いない。さらに、国内製品の便乗値上げや、生産性向上の圧力による人件費の急上昇など、最終的には殆どの産業において国内生産コストの増加が懸念される。
製造業においては、まさにその影響が最も顕著である。勿論アメリカのゴールとしては製造業の国内回帰を最終目標としているようだが、例えば昨今、常に話題に上がっているスマートフォンはAppleをはじめ、ほぼ全数が海外生産。特に中国での生産が主だ。このままいけばアメリカでの価格は単純に倍以上になる。そしてスマートフォンどころかパソコン、家電製品などは殆どがアジアや中南米からの輸入品。そればかりか製造機器や設備に使用する電子部品、加工部材なども輸入品が殆どだ。世界一の半導体製造設備メーカーであるアプライド・マテリアルズは、自社で生産する半導体製造設備のうち少なくとも数千億円分の資材は海外からの調達で賄っている。TeslaのEVでさえ、バッテリーやモーターは国内生産だが、タイヤは韓国製であり、電装品の殆どは日本や東南アジアを始めとしたサプライチェーンからの調達である。Teslaに限らず、GMやFordといった老舗のアメリカ自動車メーカーも輸入部材の調達状況は同じであろう。
そして、製品価格のみならず、アメリカは鋼材にも何と25%の輸入関税を適用。加工部材等で最も需要の高い材料なのでアメリカ国内で「ものづくり」を復活させても原材料の値段が高騰してしまっては、当然、製造コストも上昇する。加えてカリフォルニアでは最低時給がついに$20を超える勢いだ。さらに新規製造に伴う設備投資を加えると、関税を含めても海外輸入品に対して競争力を欠く状況になるのではないか? そして原材料の輸入価格、製品の製造コストの上昇により、製造業者は価格を引き上げざるを得なくなり、最終的には消費者がそのコストを負担するという状況が目に見えている。結局、関税は直接的および間接的に物価を押し上げ、国民により多くの負担を強いる要因になる。つまりアメリカに住む国民自身が実情として物価高の矢面に立たされることになるのだ。
日本からの輸出品に対しても関税が引き上げられれば、その負担は全て日本企業にのしかかる。著者も日本を中心としたアジアからの輸入業が生業なので、4月以降、輸入品にかかる税金が驚くほど高く、運送業者から請求書が届くたびに落胆を隠せない状況だ。特に自動車産業をはじめ電子機器産業など、アメリカ市場に依存している日本の産業にとっては大きな打撃となることは間違いない。
現在、日本政府はアメリカに特使を派遣し、個別の交渉をスタートしたが(4月16日時点)、日本だけ特別措置が施されることは難しい可能性がある。この先、経済のグローバル化が既に確立された中でこのような複雑な貿易戦争が勃発すれば、貿易依存度の高い日本が受ける影響は計り知れない。
ただ、そのままではダメだ。政府に頼るだけではなく、大企業に限らず中小の輸出企業も自社でグローバル化に対するチームを作り、体制を整える必要がある。先に挙げたように相互関税が施行されれば、少なくとも現時点では他のアジア諸国より日本の関税率は低い。ここに何とか商機を見い出せないか? また、自動車部品であればアメリカ依存の既存メーカーから、今やEVでは10兆円以上の売り上げを確保しているBYDなどの中国やアジアのEVメーカーへの切り替えを図れないか? このあたりも前向きに考えてもらえたらと思う。
最後になるが、現在のアメリカにおける貧困問題や国内産業の衰退は、30年以上アメリカに在住している自分の経験から、決して海外からの安価な製品輸入によるものだとは思えない。車を例にとってみても、アメリカ国内のアメリカブランドの占有率は2023年で51%で、アメリカ人の半数は海外ブランドの自動車を保有している。因みに日本は90%以上が国産車を保有し、日本車がアメリカを席巻し始めた1980年代から議論されている状況に変わりはない。まず、アメリカの自動車メーカーは、アメリカ人の欲しがるような車を作ることから始める必要があると思う。「日本はアメリカの車を1%しか買っていない」と叱責していたトランプ大統領は日本に車を売りたいのなら、例えば右ハンドル車の製造など、日本市場で売れる車の開発や生産に注力することが先決だと思う。そして現在のアメリカにおける所得格差と貧困問題の根源は、海外からの輸入品ではなく、日本の年間GDP総額の590兆円に匹敵する時価総額のNVIDIAをはじめ、AppleやAmazon、GoogleやTeslaといった巨大ハイテク企業がもたらした人件費や物価の高騰、そこにおける西部・東部と中西部間における貧富の差の急速な拡大に加え、既存産業との軋轢が要因であることもしっかり理解する必要がある。

 国際
国際