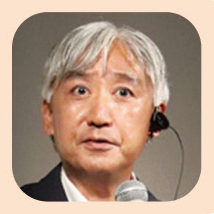『日経研月報』特集より
Stanford Professor George Foster Sports Innovation Conference 2025~日本のスポーツ産業の成長産業化に向けて~
2025年10-11月号
1. はじめに
2025年6月18日、三井不動産(株)及び(株)日本政策投資銀行共催の下、東京・日比谷にて「Stanford Professor George Foster Sports Innovation Conference 2025」が開催された。これは、スポーツとテクノロジーの未来をテーマにした国際カンファレンスとして、2014年からスタンフォード大学ビジネススクールで「Sports Innovation Conference(注1)」を主催してきたジョージ・フォスター氏の協力のもと、日本で初めて実現されたものである。
日本では、スポーツ市場規模15兆円を目指しさまざまな取組みが進められてきたが、スポーツビジネスにおいて世界トップを走る米国と比較すると、成長の余地は大いにある状況である。そうした中、近年ではプロスポーツリーグの活況や、先進的なスタジアム・アリーナの整備が各地で進んでおり、スポーツがもたらす「社会的価値」や「経済的価値」の創出がより一層期待されている。
本カンファレンスでは、米国からスポーツビジネス分野で多数の業績を有するスタンフォード大学ビジネススクール教授のフォスター氏が来日し、米国の最先端の動向を含む基調講演が行われたほか、国内外の多彩な登壇者によるパネルディスカッションや意見交換が活発に行われた。

2. 基調講演①:スタンフォード大学 ジョージ・フォスター氏
スポーツビジネス分野の第一人者として知られるフォスター氏には、「スポーツイノベーション」をテーマに、世界のスポーツビジネスの潮流と今後の展望についてご講演いただいた。

近年のスポーツビジネスの潮流としては、世界各国における女性スポーツリーグの振興や、ピックルボール等の新たなスポーツリーグの誕生、既存リーグの試合数増加が顕著なトレンドとしてみられる。
また、スポーツのメディアコンテンツとしての著しい価値向上はスポーツビジネス界に革新をもたらしている。アスリートの持つブランド力を活用しつつ、YouTubeやNetflix等のメディアを通じて世界中にコンテンツを配信することで、従来のような試合のテレビ放映だけでは難しかった、多種多様で効率的なマーケティングが可能となった。アスリートやチームのブランディング強化のみならず、関連商品のマーチャンダイジング、スポンサーシップの拡大等が促進されていることは、近年の大きなスポーツイノベーションのひとつである。
今後急速な拡大が見込まれるスポーツテクノロジー市場では、特にスマートスタジアム関連の市場規模拡大が期待されている。従来のスタジアム運営における主な収入源はチケット収入であったが、AI等のテクノロジーを活用し、イベント内容やフード、グッズ等に対する顧客の行動分析を行うことで、収益力の向上が可能となった。このような顧客分析をはじめとしたテクノロジーの活用が、スタジアム運営の革新を促進している。
更に、スポーツ産業におけるテクノロジーの活用と他の産業が相互に生み出すイノベーションの創出可能性にも期待が高まる。例えば、社会全体でセキュリティへのニーズが強まる中、スポーツイベントにおいてもセキュリティの重要性は年々増しており、オリンピックでも近年最も増加している経費はセキュリティ関連の費用となっている。また、スポーツ産業におけるAIトレンド予測には「怪我の予防」が含まれるが、ウェアラブルデバイスの活用や睡眠トラッキングといった一般向けのヘルスケア技術にも活用される要素が多く含まれる。このように、スポーツ産業における技術・サービスと一般向けの技術・サービスが相互に機能を高め合うことで、汎用性の高いイノベーション創出に繋がることが期待される。世界で最も収益を生み出しているスポーツリーグであるNFLにおいても、収益化において重要なのは、マーケティングチームによるイベントのポートフォリオ化やリーグのブランディング、メディアの使い方等の巧みなマーケティング戦略であり、選手はあくまでもアンバサダーである。
スポーツ産業は他の産業から切り離された独立した存在ではなく、むしろ多様な産業と深く結びついており、その繋がりを強化するマーケティングの重要性を改めて強調したい。
3. パネルディスカッション①:GSB Alumniの取組み
パネルディスカッション①では、スタンフォード大学ビジネススクール(GSB)の卒業生でありフォスター氏の教え子でもあるタインチャイ・ピシットウッティナン氏をゲストに迎え、自身のバックグラウンドや起業に至った経緯、今後の展望についてご講演いただいた。
ボクシング・ムエタイジムを経営する一家のもとに生まれ、幼少期から格闘技業界に親しむ中で、母国・タイにおけるスポーツ業界の発展に貢献したいという思いを抱くようになった。その後GSBに入学し、フォスター氏の講義の中で、米国の衛星放送及びケーブルテレビ放送局であるHBOのピーター・ネルソン氏(HBOスポーツ部門の当時の責任者)が外部講師として講義を行うことを知り、彼と直接話が出来るようフォスター氏に懇願した。ネルソン氏との対話の機会を活かし、約1年間の交渉の末、マディソン・スクエア・ガーデンにおけるシーサケット・ソー・ルンヴィサイ氏(タイ出身ムエタイ選手)の世界タイトルマッチの開催という素晴らしい快挙を成し遂げた。当時母国では衰退傾向にあったムエタイをグローバルスポーツとして育て上げるという展望のもと、帰国後にはタイ最大のメディア企業であるPlan B Media Public Companyと共にGlobal Sport Ventures(GSV)を創設した。
その後2022年には、世界初のムエタイ・スタジアムである、ラジャダムナン・スタジアム(1945年設立)の全面改装に携わり、スタジアム、そしてムエタイ全体のリブランディングに取り組んだ。スタジアム改装前は、来場者の9割以上がギャンブラーであったが、改装後は海外からの観光客が8割以上を占め、残り2割のタイ人については、女性を含む若年層も多く取り込み、幅広い客層が足を運ぶスタジアムへと生まれ変わった。スタジアムの改装に加え、イベント面においても挑戦的なプロモーションを展開している。DAZNを通じて世界200か国以上に配信される「RWS(ラジャダムナン・ワールド・シリーズ)」の開催や、イギリス、パリ、スペイン、東京等世界12都市で行われる「ロード・トゥ・ラジャダムナン」と呼ばれる興行も実現している。更に、試合会場の整備やイベントのプロモーションに留まらず、若い世代の選手の育成支援にも取り組み、ムエタイ業界全体のエコシステムの発展に貢献している。
今後の展望は、ラジャダムナン・スタジアムをハブとし、世界中のムエタイ愛好者や関連団体を含む国内外のコミュニティと連携しながらムエタイの基盤を築き、いつの日かムエタイを国際オリンピック委員会等で国際的に認められるグローバルスポーツとして育て上げたいと考えている。
4. 基調講演②:(株)ディー・エヌ・エー 代表取締役会長 南場 智子氏
インターネット業界のフロントランナーとして革新を牽引してきた南場氏には、ディー・エヌ・エーが手掛けるスポーツ・街づくり事業、そして日本のスポーツ産業の未来というテーマのもと、スポーツが社会に果たす役割や、新たな産業としての可能性についてご講演いただいた。

当社のスポーツ事業は、2011年12月に横浜ベイスターズを取得したことからすべてがはじまった。当時の球団は、毎年20~30億円の赤字経営となっており、チームの戦績としても5年連続最下位を記録していた。ところが現在では、3.4万人収容規模のスタジアムが2025年に開催したすべてのホームゲームにおいて満員札止めとなり(2025年6月17日時点)、年間30~40億円の黒字を達成している。チームの戦績も、2022年以降Aクラス(上位3位)を維持しており、2024年には日本シリーズ優勝まで上り詰めた。スポーツチームのマネジメント経験のなかった当社が何を行ってきたのか。
日本では米国と異なり、スポーツをビジネスと結び付けることは歓迎されない風潮があるが、まずはチームを強くする前に、ビジネスとして自立させることを基本的な軸として打ち出した。この軸のもと、大きく三つのことに取り組んだ。一つ目は監督や選手のファンサービスの強化である。運営側はこれが当然だと考えていたが、選手の中にはファンがチケットを購入するだけでなく、ファンの存在がスポンサーを呼び、広告収入が得られることで練習環境の整備や選手の報酬に繋がるというメカニズムを理解していない者もいた。このメカニズムを再度説明することで、ファンサービスの重要性を監督や選手に伝えた。二つ目は、観戦体験の向上である。例え負けたとしてもお客様に「楽しかった」と感じていただける環境を作るため、スタジアムの改修や顧客ターゲットの明確化に取り組んだ。更に、イニング間のイベントや特別企画チケット等、小さな取組みを積み重ねて観戦体験の質を向上させた。三つ目はスポンサー営業の強化である。これらの取組みを経て、最終的に黒字化に至った最後の構造改革は、2016年1月に完了した横浜スタジアム運営会社の株式公開買付けであった。スタジアム運営会社と球団の収支を統合することで黒字化が達成され、また、運営面でもスタジアムとチームを一体的に運営することで、よりスピーディーなサービス・環境改善が可能となった。また、1年のうちスタジアムでプロ野球の試合が行われるのは僅か70日で、残り290日は試合がないという課題に対しては、屋根がない環境を逆手に取り、屋外の楽しさを全面に押し出したさまざまなイベントを開催することで事業機会の拡大に繋げている。
現在は、事業の更なる空間的な広がりに着手しており、横浜スタジアムに隣接する旧市庁舎街区の再開発事業にコンソーシアムの一員として携わっている。2026年春開業予定のBASEGATE横浜関内は、ホテルや商業施設、オフィス等を含む複合型エンターテイメント施設で、当社は、ライブビューイングアリーナとVR技術を活用したエデュテインメント施設(教育と娯楽を融合させた施設)の企画運営を担う。更に、当社はBASEGATE横浜関内に面した大通り公園のPFI事業も受託しており、このようにスタジアムの熱狂を街全体の盛り上がりに繋げられることも、スポーツ事業の面白みの一つであると考える。AIにより機械的に作り込まれたコンテンツが多く広がっている中で、決して作り物ではないスポーツは、人々の本物の喜びを引き出す魅力的なコンテンツとして今後更に価値を高めていくであろう。
日本と米国のプロスポーツリーグの市場規模を比較すると、日本のプロ野球市場が2,200億円規模に対し、MLBは1.8兆円規模と、格段の差があるのが現状である。しかし、日本のスポーツコンテンツには、ポケモンやスーパーマリオと同様に独自の価値があり、コンテンツ輸出に力を入れることで、産業価値の好循環を生むポテンシャルがあると考える。今後は、一社の経営視点に留まらず、産業全体の価値の最大化へ視野を広げ、他球団とも連携しながら、次なるフェーズにステップアップしていきたい。
5. パネルディスカッション②:スポーツによる街づくり
パネルディスカッション②では、(株)NTT 櫻井 稚子氏、三井不動産(株) 松野 健太郎氏、(株)日本政策投資銀行 宮川 暁世が、各社の取組みについて紹介した。パネリストの主なコメントは以下のとおり。
当社では、携帯事業で蓄積した国内1億人規模の会員基盤を活かし、エンターテイメントやスポーツといったコンテンツの価値の最大化に注力している。IGアリーナ(2025年7月開業)での大相撲名古屋場所の開催にあたっては、海外版dアカウントを開設したところ、世界中のお客様からデータを取得できるようになった。国内外の来場者を含めた地域全体のデータ分析を進めることで、観光産業や地域経済の活性化を図り、ひいては日本経済の発展に寄与できると考える。
当社のスポーツ・エンターテインメント事業部では、スタジアム・アリーナに投資し、1日単位で利用者に貸し出す不動産事業を行うことで、商業施設をはじめとする三井不動産の他施設とのシナジーを生み出している。いずれの施設においても、稼働率を高めるため、スポーツだけでなくコンサートやコンベンションイベントも開催できる多目的スタジアムにこだわっている。また、スタジアム・アリーナを単体で運営・保有するのではなく、隣接する商業施設等の運営も含めたミクストユース(複合用途施設)の街づくりを実現することで、隣接施設の価値向上と合わせ、全体の採算性を確保できると考えている。
当行では、2012年よりスマート・ベニュー研究会を立ち上げ、スタジアムやアリーナを単体で捉えるのではなく、周辺エリアのマネジメントも含めた複合的な交流拠点、いわゆる「スマート・ベニュー」として整備することを提案してきた。ファイナンス面では、2018年よりスポーツクラブやアリーナ事業者への投融資を行っている。スポーツの成長産業化に向けては経済的な自立が重要な課題となっているが、残念ながら、現時点では日本にはまだ収益性や事業性の高いスポーツ事業が多くないのが実状である。その構造的な要因を明らかにするため、2025年8月に海外と日本のスポーツ産業における資金循環や収益構造の違いを分析した書籍を出版する。
6. パネルディスカッション③:選手・顧客体験の向上と新たな事業機会創出
パネルディスカッション③では、(株)アシックス 甲田 知子氏、スクラムベンチャーズ 宮田 拓弥氏が、各社の取組みについて紹介した。パネリストの主なコメントは以下のとおり。
当社は、2020年にコロナの影響を受け赤字となったものの、その後毎年大幅に利益を伸ばしている。地域別売上高では、日本の売上は13%程度であり、最も大きな市場は欧州、北米、中国と続き、今後も更なる成長を見込んでいる。2023年に刷新した当社のデザイン・フィロソフィーとして、①ユーザーテスト、②サイエンス、③イノベーション、④サステナビリティを掲げている。イノベーションについては、アクセラレータープログラム等に取り組み、従来は内製化していた素材の開発も、積極的に外部のパートナーとの連携を模索するようになった。また、最も大切にしている「ユーザーテスト」については、トップアスリートのインサイトを重視し、2023年からは科学的な検証が十分でない場合でもアスリートの意見を優先した製品開発の方針に転換した。近年のスポーツ業界の変化として、スポーツ産業がトップアスリートのためだけではなく、いかに地域の老若男女の心身のウェルビーイングに貢献できるかが重要な観点となってきている。
当社では、スポーツテックに特化したファンドを立ち上げ、スポーツリーグや学生スポーツ等、約20社に投資している。知名度の高いスポーツチームと、知名度は低いものの技術とパッションを持つスタートアップを支援するこのファンドは、実は良い組み合わせであり、日本でもファイターズと連携し国内初のスポーツチームのファンドを組成した。また、学生スポーツは日本ではビジネスに繋がらないイメージを持たれるが、米国の学生フットボール市場規模は約2兆円と、MLB市場(1.8兆円規模)よりも大きい。日本でも高校野球や早慶戦等、人気のある学生スポーツが存在し、これらのマネタイズが、スポーツ市場規模15兆円達成のカギとなるだろう。近年のスポーツ業界における大きな変化として挙げられるのは、ファンとトップアスリートの関係性の変化にある。これまでは、アスリートの素晴らしいプレーをファンが観戦することが主な消費行動であったが、ソーシャルメディアによって、アスリートとファンが直接エンゲージできるようになった。観客動員数や売上等も重要な指標であるが、これからのスポーツビジネスでは選手自身が有するインフルエンス力を示すフォロワー数等がより重視されるのではないか。
7. 総 括
カンファレンス当日は、多彩な基調講演とパネルディスカッションに加え、スタンフォード大学アメリカンフットボール部コーチ 河田 剛氏による開催経緯説明や、一般財団法人日本スポーツ政策推進機構会長 遠藤 利明氏、(株)読売新聞グループ本社代表取締役社長 山口 寿一氏らによる来賓挨拶、(株)日本政策投資銀行代表取締役会長 太田 充による閉会の挨拶で幕を閉じた。
来賓挨拶においても言及があったように、米国におけるスポーツ産業の規模に対しては依然として及ばない部分はあるものの、日本におけるスポーツ産業の潮目は、テクノロジーの革新や関係者の取組みの強化等に伴い近年確実に変化しつつある。(株)日本政策投資銀行としても、今後もスポーツ産業界の意識改革を促す情報発信やスポーツ事業へのファイナンスを通じて、各スポーツ関連事業者との連携を一層強化し、スポーツ産業の成長産業化に向けた取組みを推進していきたい。
(注1)NBA(ナショナル・バスケットボール・アソシエーション)やMLB(メジャーリーグベースボール)、NFL(ナショナル・フットボール・リーグ)などのプロスポーツリーグの経営陣や、世界の先端を走るメディア・IT企業、スポーツテック系スタートアップのリーダーたちが集まり、スポーツ産業の革新と成長について議論する場として、毎年大きな注目を集めている。

 スポーツ
スポーツ