World View〈アメリカ発〉シリーズ「最新シリコンバレー事情」第10回
AIによる大淘汰時代をどう捉えるか?
2025年12-2026年1月号
シリコンバレーでは連日のようにAIに関連したニュースが地元の放送局から流れている。最近はWebで見ることが普通になった新聞でも状況は全く同じ。ご存じのように2023年のChatGPTのリリース以来、その需要と市場への浸透が、まさに指数関数的に増大している様子が毎日の報道から伝わってくる。シリコンバレーを走る幹線高速道路101号沿いのアナログの広告塔にも聞いたことのないようなAI企業の広告がやたらに目につくようになったのは昨年頃からだ。
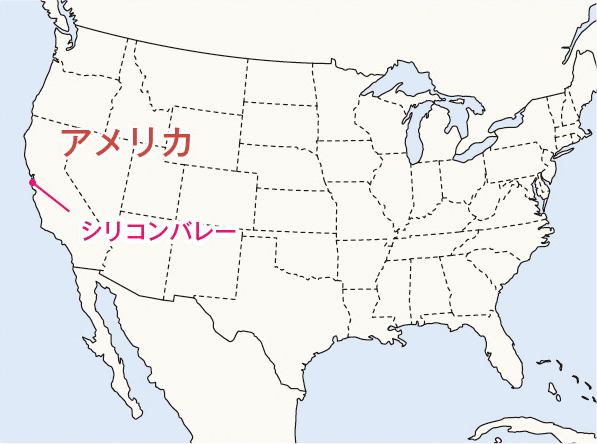
現在シリコンバレーにあるAI関連企業は、スタートアップを含めると数百社にもなる。シリコンバレーの著名なベンチャーキャピタルであるセコイアキャピタルとForbesが共同発表した「AI50」のリストに掲載された50社(シリコンバレー以外の企業も含む)は、売上はまだ公開されていないものの、評価額が1,000億円を超えるユニコーン企業が殆どだ。
当然、IT最大手のGoogle(DeepMind)、Meta(AI Research)、Apple、NVIDIA、Teslaなども、独自のAIサービスや専門のAI事業部・研究拠点を持ち、先行するOPEN AIの牙城に猛追している。現状では、これら大手が提供するサービスは基本的にインターネット普及期に注目を集めた検索ポータルサイトと同様に、ビッグデータを活用したスタンダードなAIツールやアシスタントが主流ではあるが、最近ではこの分野も、個人に適したツールとしての性格が強まり、「AIエージェント」や「AIサーバント」といった表現で呼ばれている。当然、巨額資金を投じた開発が主流なので、サービスの精度や質も日進月歩で進化している。
加えて、これら膨大な情報処理を必要とする、AIをつかさどる半導体企業やデータセンター構築に不可欠なインフラ企業も動きが加速している。既にAI半導体分野では超巨大企業になったNVIDIAをはじめ、老舗ながらもAI半導体に特化して業績を伸ばしているAMDやIntelも存在感を強めている。またネットワークインフラでも新興勢力Crusoe、GPUクラウドをつかさどるLambdaなども関連産業として今後の隆盛が見込まれている(勿論、熾烈な弱肉強食の世界になるとは思う)。
さて、前述の「AI50」に掲載された企業に代表されるように、昨年頃から、AIが各業種の実務を支援する方向へと進化する傾向が顕著になってきた。言い換えれば、既に数百社存在するAIのスタートアップは、基幹アルゴリズムの開発ではなく、医療、法務、会計、報道、通信、製造など各業種に適合したAI開発に特化し、その分野でのデファクトスタンダードを確立することで業績を伸ばしている。例えば、語学学習AIのSpeak、医療情報AIのOpen Evidence、法律業務効率化AIのHarveyなど、いずれも既に評価額1,000億円以上のユニコーン企業に成長している。
自分が長年携わっている「ものづくり」の製造プロセスにおいても、急速にAIの導入が始まっている。生産や在庫管理等は、従来の人海戦術から、AIの利用により迅速かつ正確に管理できるようになってきた。さらに生産ラインでは、工程管理にかかわる「稼働率」や「べき動率」のより明確な把握、消耗部品の耐久性や交換時期の管理、生産不良の解析による工程管理や品質の向上に繋げるための「カイゼン」データもAIを使えば精度の高いものになることが明白で、この分野への導入が急ピッチで進んでいる。
かつてAIは知的/高収入職業の凌駕が第一の目的とされていたが、最近では各業種への浸透が進み、人手に頼っていた領域がAIに置き換えられる流れが主流となり、幅広い業種で人員削減が進む傾向がはっきりしてきた。2025年に入り、Googleの数千人規模のレイオフ、Metaが3,600人、元祖シリコンバレー企業の代表格ヒューレットパッカードの2,500人をはじめ、シリコンバレー以外でもAmazonやMicrosoftが数千人規模のレイオフを敢行。2025年上半期だけで5万人以上が職を失っている。
シリコンバレーでは、その流れが特に顕著だ。主に営業、経理、総務、カスタマーサポートなどの職種がAIに置き換えられている。加えて今まで、この地では花形職業で常に需要もあったソフトウェアエンジニアも昨今のプログラムや回路設計などのAIによる自動生成の発達により、その需要が淘汰されつつある。また、MetaのようにAIが主流になる時代に生き残れない“低業績社員”を早期退職に導くような動きも出始めた。
このようなレイオフの嵐が吹き荒れる状況で解雇されてしまった場合、再就職もAIによる業務の自動化に伴い相当厳しい状況のようだ。日本の大手電機メーカーで20年以上ハードウェアエンジニアとしてのキャリアを持ち、ヨーロッパの大手通信メーカーでITネットワークのインフラ構築という先端の技術フィールドで活躍、その後も大手自動車メーカーでの開発などを担ってきた友人は、これだけのキャリアがありながら、この春、勤務先の事業撤退によりレイオフされたあとの再就職活動で、100社以上の会社に履歴書を送っても面接までたどり着けたのは1社もなかったと話していた。実は同様の話しを複数の知人からも聞いている。今後はAI関連企業に勤めていても、AI中心の世の中という先々の需要の変化で全く予断を許さない現状なのだ。現時点でアメリカでは企業のAI導入率(単純な検索作業も含む)は全体平均で80%以上であり、この流れと就職難はさらに加速しそうな勢いだ。
さて日本はどうか? 現時点での企業によるAIの業務導入率(これも単純な検索作業も含む)は全体平均で約56%で、世界平均値と同水準だが、導入しても活用の質などの問題もあるので、この導入率がイコール効率化に直結しているとは思えない。日本企業ではレイオフが難しい商慣習があるため、AI導入による業務の割合が今後増大しても、従業員を確保し続ける必要があるのか?それによって人件費が財務を圧迫し、業績に影響を及ぼすことは間違いないが、このあたりをどう捉えていくのか? 本当に余計なお世話かも知れないが、一足先にAIによる大淘汰時代が始まっているこの地の状況を見る限り、この先、間違いなく同じ状況が訪れるであろう日本の近未来が何とも気になって仕方がない。
※アイキャッチ画像に使用している写真は、AI用半導体で圧倒的なシェアを持つNVIDIA本社。宇宙船のようなデザインが目を引く。遠藤氏が撮影したもの。

 AI・デジタル化
AI・デジタル化 