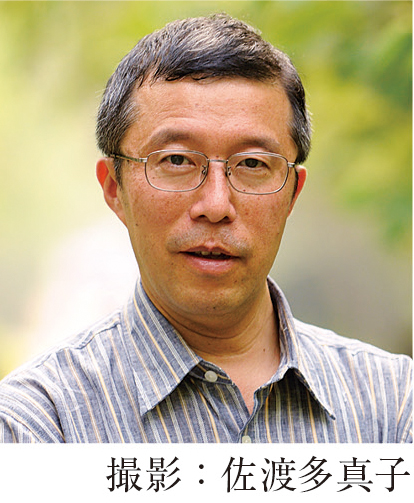World View〈アジア発〉シリーズ「アジアほっつき歩る記」第113回
中国 江蘇省揚州の美食旅
2025年12-2026年1月号
前回は広東省美食旅をお伝えしたが、今回は揚州(江蘇省)の旅をご紹介したい。揚州は日本ではあまり知られていないが、「揚州炒飯」などが有名な美食の街。何と筆者が揚州に行ったのは38年前の上海留学以来であり、当然街には大きな変化があったが、今回は食にスポットを当ててみたい。

38年ぶりに揚州で炒飯を
上海留学中の1987年、どうしても「揚州炒飯」が食べたくて、上海から苦労して訪れたことは良い思い出だが、どんな味だったのかはあまり覚えていない。ただなぜ中国で揚州炒飯がこんなに有名なのか、は常々疑問に思っていたので、今回は38年の時を経て、改めて揚州に行ってみた。
揚州の料理は「淮揚菜(わいようさい)」と呼ばれ、古くから中国四大料理の一つに挙げられる、伝統的な食べ物だ。揚州自体が大運河の開通で唐代から栄えており、明代以降は塩取引で財を成す商人を輩出、彼らの財力が美食を生み出したともいえるだろう。清代の乾隆帝はわざわざ北京からこの地を6回も訪れたといい、その美食を堪能している。揚州炒飯が名を馳せたのも、流通の拠点と何やら関係がありそうだ。
今回揚州へ行ってみると、炒飯もかなり進化している印象。川沿いには新淮揚菜と書かれたレストランがあり、何となく美味しそうだったので入ってみると、揚州名物になっている「獅子頭」はそのあっさりしたスープが予想以上に美味。だが最大の目的、炒飯はやはり難敵で、スタッフも“さすがに一人では普通の中国人でも食べ切れない”と言われてしまった量(日本の2~3人前)だった。

揚州炒飯はいわゆる五目炒飯であるが、更に現在は創作料理の傾向もあるので、彩が良く何とも旨そう。ご飯は一般的にパラパラ系で、卵(ここの店ではかなり細かい)、エビ、ハム、キノコ、鶏肉、干し大根、グリーンピースなどで構成されている。メニューにはちゃんと米350gなどと分量まで書かれている。非常になめらかな炒飯という印象で、塩気は抑えめでも味はしっかりしていて、思わず旨いと唸ってしまった。
もう一か所、38年前に食べた揚州賓館のレストランへも行ってみる。ここは敷地が非常に広く、ゆっくり散策すれば1時間あっても足りないほどだが、この散歩で腹を空かせて炒飯に挑み、300gを完食した。更にはとろみのある「文思豆腐」も好みの味で感激。揚州は豆腐料理も有名で、このあたりは何となく京都を思わせるものがある。
因みに揚州賓館の敷地には痩西湖があり、その先の趣園という場所に繋がっている。今回は残念ながら食べることはなかったが、趣園茶社で飲茶を楽しむのも一興かもしれない。食後はフラフラ歩いて、かの鑑真和上ゆかりの大明寺を訪ねるのも良い。遥か奈良時代の日本と揚州は繋がっていたのだ、と考えるだけでも歴史ロマンがあり、また揚州の重要性が分かる。
実は街中でも「茶社」という文字をよく見かけた。これは揚州独特の「茶楼(茶館)」なのだろうか。その一つに実際に入って飲茶を味わってみた。歴史もかなり古そうで、メニューを見ると、本格的なレストランだった。
料理を頼むと花茶が自動的についてきた。料理は「焼売」と「三丁包」という点心、そして「淮揚煮干絲」。焼売は肉が入っていないタイプで形は火口型。三丁とは鶏肉や筍の角切りを入れて蒸した包子。特に美味しいと感じたのは煮干絲。豆腐の細切りをスープで煮たようなものだが、このスープが実に繊細で味わいに奥深さがある。淮揚菜は作りが精緻で、味はかなりまろやか。どんな風に作るのか、いつかその製法を勉強してみたい。
揚州人は普段何を食べているかよく分からないので、街中のチェーン店も探索してみた。「揚州湯包」は薄い皮に豚肉と蟹味噌がとろけて、肉汁がたっぷり包まれている食べ物。これは台湾で食べる小籠包より美味いかもと思ってしまう味。でも上手に食べないと蟹味噌はすぐに外へ出てしまう。もう一つはエビワンタン。ワンタンが小さくていくつも入っている。スープがちょっと辛くて意外な感じが良い。チェーン店でも味のレベルはかなり高い。揚州人は毎日こんな質のよい物を食べているのかと、羨ましくもなる。
最終日の朝も飲茶を食べることにした。日本人は飲茶をランチに食べると思っている人が多いが、実は中国では朝食べるもので、「早茶」と呼ばれている。飲茶は明代の揚州が起源(そこから清代に広州へ伝わった?)と聞いたことがあったが、どうだろうか。ただ早茶の看板はよく見かけ、この地に根付いている様子が窺われる。のんびりした店内で、点心として「五丁包」(前回は三丁包)を頼み、主食は「腰花煨麺」を注文してみる。

煨麺を一口食べてスープを飲んですぐに気が付いた。この麺のふにゃふにゃ具合、鶏のいい感じの出汁スープ、これは香港などで食べていた麺だ。何でこんなところにあるのだろうか。いや、元はこちらから香港や広州へ伝わったのではないか、などと考えていると頭が忙しくなり、味が分からなくなる。まあご多分に漏れず麺の量は非常に多いので苦労する。
因みに揚州から高速鉄道ですぐ行ける古い街、鎮江には名物「鍋蓋麺」がある。黒いスープに細い魚と腸、そしてコシのあるちじれ麺が入っていた。これが思っていたより旨いのだが、秘密は地元独特の酢にあるらしい。揚州と鎮江は隣同士でも、その食文化の成り立ちは全く違う、と感じられる。
この広い中国にあって、ほんのわずかな距離でもかなりの違いがあるのだから、日本でいう「中華料理」なるものが中国にないのは当然である。各地の料理の中には広い範囲に伝播しているものもあり、その歴史的な背景や成り立ちを調べるのは決して簡単ではないが、料理が各地名を冠して呼ばれるのは、この広大な中国において当然のことと言えるだろう。

 アート・文化・食
アート・文化・食