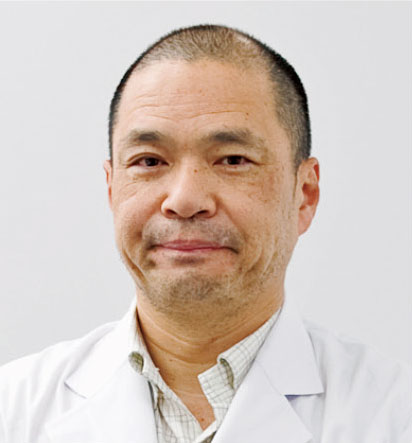『日経研月報』特集より
医師はどのように人々の健康に向き合うか ~医療と介護のサステナビリティ(第11回)~
2026年2-3月号
本連載の第11回は、長野県佐久市にある佐久総合病院で、地域医療部地域ケア科医長を務める色平哲郎氏にお話を伺いました。今回の取材は、2022年に本誌で4回にわたり連載された『コモンズを巡る旅』(酒巻弘氏執筆)が契機となっています。
宇沢弘文教授と親交を深めてきた色平氏がその連載の存在に気づき、当時同連載の編集を担当していた筆者も含めてやりとりを重ねる中で、今回、「健康・長寿・幸せ」をテーマにお話を伺うこととなりました。
長野県は医療費を抑えながら長寿を実現した県として紹介されることが多いのですが、その中でもJAが運営する佐久総合病院を中心とした佐久エリアでの地域ケアは長く注目を集めてきました。今回はその歴史的背景についても解説いただきます。

1. 医療への本来的なニーズと予防医療
-色平先生は佐久総合病院に赴任されて30年以上になると伺っています。NHK長野放送で2000年に放送されたドキュメンタリー番組を今回の取材前に拝見しましたが、そこでも語られている地域医療への出発点についてお聞かせください。
色平 1990年に京都大学医学部を卒業後、この病院で研修を受け、その後1996年にこの病院に戻ってきました。ご覧いただいた放送の当時、私は南相木村という人口1,300人の村で診療所長を務めていました。農家の方の暮らしを深く知ることが農村医療の第一歩であるというのは、後ほどお話しする佐久エリアの伝統でもあり、実際に30分以上かけて世間話をし、普段から心を通わせて必要な医療を提供するという取組みを行ってきました。
ただ、あの放送で描かれたことは「国民の医療に対する素朴な期待」をなぞった構成となっている部分があります。
その「素朴な期待」とは何だと思いますか。それは「どこかに、病気になったときに治してくれる良い医者がいてほしい」という期待です。でも、実際に自分が病気の当事者になったときに「本当に怖い病気」とは何だと思いますか。
-(少し黙る)
色平 本当に怖い病気というのは「死んでしまう」病気です。そして、その「死んでしまう」病気には大きな特徴があります。それは、あまり症状が出ないということです。だから手遅れになる。急性の病気は救急などで対処できますが、こうした病気、英語で言うと「insidious」、つまり知らぬ間に進行する病気が怖いのです。そうした病気に信州は対応してきました。
それはどうやったらできるのでしょうか。症状もない、医者にかかりたいとも思わない、この忙しいのになぜ、という皆さんの気持ちを乗り越えて対処していく必要があります。そこで先般ご覧いただいた映画の話につながります。
-『腰のまがる話(注1)』というGHQにより1949年に作られた映画ですね。
色平 あの映画を見た映像作家の友人は「入り口がうまい。痩せるためにはどうしたらいいか、肌が綺麗になるにはどうしたらいいか、といった話と同じような導入で、腰がまがらないようにするにはどうしたらいいか、といった入り口になっている」と言っていましたが、本当にうまい作りですよね。
そして、あの映画は実際にこの佐久地域で撮影されました。今も残る山並みなどが、そのままの形で映っています。そして、「早めに病院にかかること、農村の女性たちが婦人部を作ること、自分たちでケアの体制を作ること」を助言する役を俳優が演じていますが、モデルはこの病院の創設者である若月俊一氏です。
-「佐久病院」という看板が実際に映像の中に映っていますね。その頃から健康を自分たちで守るという伝統がこのエリアにあるということでしょうか。
色平 今の時代、「長生きをしたければ、どうしたらいいか」は推論できます。例えば2~3年おきに胃カメラを受けます。そうすればまず胃がんは早期に見つかる。食道もその時にわかる。もちろん難しいがんはあります。例えば膵臓がん、女性の卵巣がんなどです。そうした意味では全ての疾病に対応するわけではありませんが、とはいえ2~3年に1回しっかりとした検査をしていくだけで死亡率は大きく下がります。
先ほど述べた「死にかねない病気についてきちんと」ということが方法論で、これは社会教育です。そうした社会教育が戦後すぐの段階から根付いているのがこのエリアの特徴の一つです。
ただし、私がここで言う「予防は治療にまさる」ということを論証するための、予防と治療それぞれの具体的な費用の詳細を調べる研究は、まだ進んでいません。今、この調査を、早稲田大学大学院の兪炳匡(ゆう・へいきょう)教授(注2)が私たちと共同で進めつつあるので、こうした研究が形になると、より社会教育も進むものと思います。
-こうした佐久の取組みについては、宇沢先生も興味を持っていたと伺っています。
色平 今の医療は、どうしても痛みなどを訴える患者に対してのサービスになる傾向があります。つまり患者が持つウォンツに応えているわけで、先ほど述べた「insidiousな病を防ぐ」という本来的なニーズに応えているわけではありません。
こうした話を2000年代前半に長野県庁の会議などで親交を得た宇沢先生にも伝えました。ただここで宇沢先生と私は意見が違った部分があります。宇沢先生は「医者は先生であり、プロフェッショナルだから、彼らが自治を行うべき」という考えを持っています。
-それが「社会的共通資本の医療」の根幹の一つだと私も理解しています。
「プロフェッション」や「プロフェッサー」の語源である「プロ」とは中世ラテン語に由来し、旧約聖書における「プロフェット」、つまり預言者は死刑になりそうな状況であってもきちんと話す人です。そうした言葉本来の意味でのプロフェッショナルな活動を現代の医者ができているか、という論点はあると思います。宇沢先生は性善説の方だと思うのですが、現場にいると、そうした観点での意見の相違はありました。
-宇沢先生は、経済学の立場から「社会的共通資本としての医療」を考えたわけですが、色平先生は現在でも現場の視点を踏まえつつ、経済学的な観点での予防の意味合いに強い関心を持たれているわけですね。
現在の話に戻ると、国民の「ニーズ」に応じて医療と社会教育を展開すれば、医療費は下がるし、健康指標も良くなる。それを佐久エリアは実現できているので、その秘密をきちんと言語化すればいい、というのが、兪先生への期待ともなります。
2. 医師はその技術で直接、人々を救いあげるのではない
-予防との関連で先生が考えられるプライマリ・ヘルス・ケア(PHC)についてご教示ください。
色平 よく政策などで言われる「プライマリ・ケア」、一次医療というのは医者が一人はいないといけません。二次では、医者が複数いて病棟がある。三次はさらにそれより高度な形です。
これに対して、「プライマリ・ヘルス・ケア」というのは国際保健の場でその重要性が叫ばれていますが、日本においては「ゼロ次医療」という私が作った造語があてはまると思います。書籍『医者のいないところで(Where There Is No Doctor)』は世界の80数ヶ国語で翻訳されています。これは教育、いや教育と言うべきではなく学習活動。人間が人間として人間の世話をするという行為は、近代医療が確立される以前から人間が行ってきたことです。こうした行為の実効力を促すという考え方なのですが、それは「その人の訴えを聞く予診の中に全てがある」という若月先生の言葉とも連なるものです。
そもそも佐久総合病院に出資したのは農家の方であり、その組合である農協に私たちは雇われています。こうした雇い主であり、一次産業の当事者である農家や酪農家と、私たち医療技術者は同じ方向を向き、共に歩むことが必要です。
ただ今日では、医学部では医者が技術を学び、人間を救うと考えられています。本来はその発想は全く逆で、医療技術を願うのは農家の方であり、患者なのです。「先生が言うのであれば、この治療でよい」といった形で患者から医者への信頼が成り立つことが理想だと思います。
-佐久総合病院では研修医をフィリピン大学医学部レイテ校(School of Health Sciences:SHS(以下、SHS))に派遣していますが、SHSの仕組みはそうした考えに近いとお聞きしています。
色平 SHSは私自身の医療の原点で、「心の母校」ですが、SHSへの訪問(1986年)がきっかけとなって佐久総合病院に勤めるようになりました。SHSのトライアルは非常に面白いものです。
SHSの学生は、最初は助産師、次に看護師となり、その後、現場で保健・医療活動の実地体験を積んだ後、「住民の75%から、ぜひこの人にもっと学んでほしい」という推薦があって初めて医学コースに進級できます。当然、学力を競うという話ではありません。事実上、フィリピンの自治医科大学なのですが、医科大学ではなく、ヘルスワーカーを育てていて、最終的に医者になってほしい人がいたら医者になる、というコースです。
SHSがなぜこういう形になったかというと、フィリピンの名門大学医学部ではやはりブレイン・ドレイン、アメリカへの人材流出があります。この状況が大変だったので、SHSを始めるしかなかったということでもあるのですが、この仕組みの中で生まれた医療技術者たちが島や山に残る割合は9割です。
本来だったら医者になる境遇でなかった人が、農民が解放され、進学できて医者になれたという歴史的構図が日本にはあります。彼らもまた同じようにSHSに入れたから医療技術者になり、そして地域に戻り、皆の役に立ちたいという強い動機付けがなされています。1986年にこのことを知り、これは日本の医学部に決定的に欠けている要素だと思い、日本に伝えようと思ったところ、この教育システム自体、若月先生の「農村医科大学」構想がベースとなり作られていると知り、それで佐久に行ってみようと思ったのが自分の原点です。
3. 「幸せ」をどう定義するか、そして社会の変化
-色平先生は、日本の健康を維持してきた一つの要因はソーシャル・キャピタル(注3)、人と人との関わり合いにあるという考え方を述べられてきました。また、昔から地域共同体を支えてきた精神が、長寿社会を幸せに生きるヒントになる、という話もなされています。
色平 先ほどの『腰のまがる話』は共助のあり方を示しています。「みんなで、できることをやる」ということは農村社会で当たり前のようにやってきたことですが、それが人々の生活と人生を下支えしてきたのだという自信を持ってよいことなのです。そうした生活の中で自らの健康を語ることは、村の幸せ、人々の幸せにつながります。
これを言い換えたのが若月先生ですね。戦争が終わった直後に、「皆さんは自分の体のことを大事に考えていいし、農民は解放された以上、自らの生計を自ら維持していくために団結して協同組合を作らなきゃいけない」と言ったわけです。
アフガニスタンを拠点に医療活動を行った医者の故・中村哲さんは、幸せとは「三食食べられて家族で暮らせること」であると言っています。「病気にならない」というのはもちろん大事な要素としてあるのですが、三食、そして家族で暮らせるということを確保できる状況が大事だと思います。
-そうした考えは、佐久で過ごす30年の間でどのように変わってきたか、お聞かせいただけますか。
色平 正直にいえばソーシャル・キャピタルとあえて言わなければいけなくなっているというのは、ソーシャル・キャピタルが失われてきているからです。地域社会の崩壊が著しいですし、高齢化も進行しています。でも、辛い状況、逆風の下だからこそ取り組むという気風が佐久にはあります。
佐久の取組みというのは、私が思うには決して勝とうとしているわけではないのだと思います。「負けない」ということだけです。
本当はこんなところに病院が維持できるはずがなかったのです。なにもないところで頑張るしかなかった人たちが、必死になって考えて、医療技術者を招いたり、来てくれた時に大切にしたりするなど、そういったことでこういう形になり、今も生き延びています。決して勝っているわけではないのです。
2012年頃、世界銀行の方がワシントンD.C.から来て、私に聞いた質問は一つで、「世界銀行からすると佐久病院は成功モデルだが、その秘訣を教えてほしい」というものでした。多くの方がそうしたことを聞きます。
それについていえば「負けなかった」ということだけです。ソーシャル・キャピタルと言う必要がないほど、ソーシャル・キャピタルに富んだ地域だったのです。実際には、『腰のまがる話』の中にあったソーシャル・キャピタルは現在、摩耗してしまっています。しかしながら、人々の立ち居振る舞いの中にそれを大事にする感覚が生きていて、それはお金では測れない価値です。
それが私たちの初期条件です。そして、何よりも、最も大きな変化が戦後の初期にそうした形で起こったため、その後は変化があっても大きくは変わらない、というのが正直なところだと思います。
-そうした状況の中でも、改善していくべき点などはあるでしょうか。
色平 私は内科医です。内科医というのはゆったりと治療を実施していく必要があります。ご覧いただいたNHK長野の映像でも、私はおじいちゃんに「2年後には必ず来てね」と軽く言っていますよね。それが早期発見につながります。医療費も下がります。
そして内科医という意味でいえば、今の日本では一般内科医が求められています。一般内科医をどう育てるのか。それは、その地域において、村の言葉、医者の言葉、行政の言葉について3ヶ国語でのやり取りできる、そうした医者です。こうした部分はしっかり対応していく必要があります。
また、内科医のやり方というのは、本来の意味での「保守」だと考えています。保守というのは劇的な改革を行うわけではありません。じっくりと物事に取り組むのがそのスタイルです。そのことはこの後の宇沢先生との話につながるものと思います。
4. 「社会的共通資本としての医療」の現代性
-それでは最後に、宇沢先生の社会的共通資本に関する話をお伺いします。宇沢先生は医療について、「医療に関わる職業的専門家が中心になり、医学に関わる科学的知見に基づき、医療に関わる職業的規律・倫理に忠実なものでなければならない」と捉えていました。
ただし、現実を考えるとこの定義と現況に乖離があるのでは、という話をここまでしてきました。
色平 ご指摘の「乖離」というのは自分の中でテーマでもあると今も思っています。それは先ほど来申し上げてきた点も含めてです。
-次に、そうした乖離があるとすると、その改善に向けた手立てはあるのでしょうか。
色平 変えなくてはいけないところは、ゆっくりと変えていくことが必要だと思います。5年かけて、10年かけて、変えていく努力とプロセスをしっかりと保持することが重要です。
そうした意味では、佐久は長い年月をかけて農業に従事する一次産業の当事者と医療技術者が相互を理解する関係を築いてきたので、多少の変化があって高齢化が進んでも、その信頼が崩れないという部分はあると思います。
そのうえで確かに色々と変化はあります。ただし、5年かけてゆっくりやらなければいけないことを一気にやるとしたら、そもそも医療自体が崩壊してしまうでしょう。
とにかく自分の頭で考えて、住民が1年、2年かけて考え、案を出してきたものを上手に議論して、これで作ろうという形に時間をかけてやっていく。病院だけの話ではなく、地域として、こうしたところは大切です。
-そうした長い時間をかけて、医療における変化への対応を行うべきであるということは、宇沢先生と様々な局面でお話をされる際にも共通項としてありましたか。
色平 はい、ございました。
-「長さ」という話でいえば、社会的共通資本における自然資本には「コモンズ」という概念があります。かつての英国でのコモンズの実例として「森林憲章(注4)」という文書があり、754年にわたって続いたものといわれており、その継続性に大きな特徴があります。
色平 森林憲章はあまりにも大事な法典です。人類の共通基盤が存亡の危機にある際に、その際であれば、森を大切にする。そのために征服王の一族が勝手に狩りをすることを締め出した。そして、それをマグナカルタと同時期にしっかりと文書として残していることが重要です。
もちろん700年もの年月をかける必要はないのですが、日本は戦後改革というものを7年ほどで行い、形を作ってきた。その際に思い切った取組みがなされて出来上がったものを、日本に今後も定着させることができるかどうか。今はその大事な転換期でしょう。
「コモンズ」という考え方は正しいと思います。日本の医療について考えた場合、国民皆保険がその位置づけにあるのかもしれません。これはなかなか他の国も模倣ができません。戦後のあるタイミングで出来上がった制度であり、他国がこれを実現しようとする際には、その根幹である「農民皆保険」をしっかりと掌握する必要がありますが、これは必ずしも容易ではありません。
日本ではこうしたことが実現するタイミングがあったということは大事なことだと思います。
-本日は、医師という立場で、社会哲学・経済学など様々な視点を有しながら、実際に宇沢先生と議論をしてきた色平先生に、これまでの取組みや宇沢先生とのお話をお伺いできたこと、大変感謝しております。ありがとうございました。
(注1)『腰のまがる話(Bent with the Years)』は、GHQ(連合国最高司令官総司令部)民間情報教育局が1949年に制作した映画。
(注2)早稲田大学人間科学学術院人間科学部教授及び神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科教授
(注3)社会関係資本。アメリカの政治学者、ロバート・パットナムの定義では「人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのできる、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴」。
(注4)1217年に制定された「The Charter of the Forest of 1217」の訳で森林の所有権に関する法律。征服王ウィリアムとその後継者によって侵食された王立の森に対して、人々の自由な立ち入り権を確立したもの。

 ヘルスケア
ヘルスケア